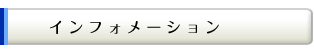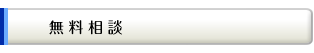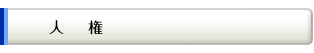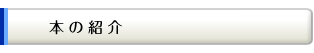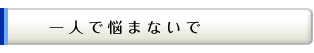核と人類は共存できない!核兵器使用のリスク拡大に歯止めを
被爆80周年原水禁世界大会
被爆80周年原水爆禁止世界大会が、福島(7月26日)、広島(8月4日~6日)、長崎(8月7日~9日)で開催されました。
ロシア・ウクライナ戦争、イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区とイランへの攻撃など、世界では核兵器の使用が現実のものになる危険性が拡大しています。
私たちは、核も戦争もない平和な社会の実現に向け、核兵器廃絶に向け運動を進めてきましたが、唯一の戦争被爆国である日本が核兵器禁止条約に背を向けたままという状況は変わっていません。
アメリカの科学雑誌『原子力科学者会報』は今年1月、人類滅亡の日の「午前0時」までの残り時間を象徴的に示す「週末時計」をこれまで最も短い「残り89秒」と発表しました。1947年にこの時計の発表が始まって以来最も「午前0時」にせまり、昨年から1秒進められました。『原子力科学者会報』は、針を進めた理由について、核兵器使用のリスクが増大していることや、人工知能の兵器利用、気候変動の進行などを挙げています。こうした現実を踏まえ、私たちは一日も早い核兵器廃絶の運動を大きく展開していかなければなりません。
原水禁運動の歴史を学ぶ
福島大会では「被爆80年 核と人類は共存出来ない~核なき世界をめざして~」と題し原水爆禁止日本国民会議共同議長の金子哲夫さんが、原水禁運動の歴史を話しました。「被爆者の救済なくして核廃絶なし、核廃絶なくして被爆者の救済なし」という言葉に象徴されるように、金子さんは核兵器廃絶と被爆者の救済が、原水禁運動の両輪であると述べました。また、1975年の被爆30年の原水禁世界大会で、核絶対否定の理念を確立したことをあげ、核の軍事利用と原発推進のなかで語られる「核の平和利用」も否定し、一貫して脱原発の運動にとりくんできた経過を説明し、核と人類は共存出来ないことを強く訴えました。
核兵器廃絶にむけ国際シンポジウム
広島大会では、国際シンポジウムが行われ、日本・韓国・イギリス・アメリカからの参加者が世界の核兵器廃絶にむけた議論を行いました。
昨年の日本被団協のノーベル平和賞受賞は、世界に大きなインパクトを与えたことが確認され、核保有国に核軍縮を進める責任を果たさせるために核兵器禁止条約を支えているグローバル・サウスの国々との連帯が重要だと確認されました。
「被爆体験者」は被爆者だ
長崎大会では、旧長崎市の外で被爆したため被爆者として見なされず、いまだに被爆者健康手帳を取得できない「被爆体験者」のたたかいが報告されました。
広島では2021年、「黒い雨」被爆者裁判の高裁判決によって、より広範な雨域にいた人々に被爆者健康手帳を交付すべきとの判決が出されましたが、長崎でも同じような状況にあったにも関わらず、国は「被爆体験者」に被爆者健康手帳を交付しようとしていません。同じ国の制度下でこうした差別は絶対に許されません。
私たちは、「被爆体験者」は被爆者だと訴えてきました。被爆者の高齢化を考えれば一刻も早く国は解決を図るべきです。
世界の動向や国内の原発推進政策など課題は山積していますが、核廃絶にむけて運動の前進を図らなくてはなりません。