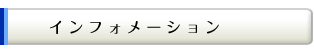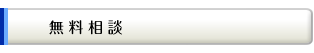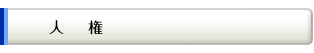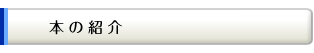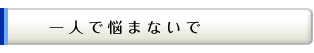成立を許すな!! 「働き方改革」に逆行する「給特法『「改正』案
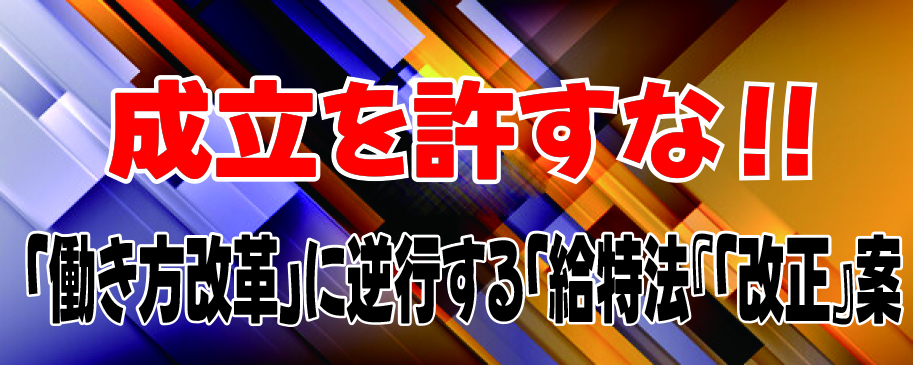
2月7日、自公石破政権は、給特法「改正」案を閣議決定し、今国会で成立させるとしました。この「改正」案は、様々な問題を持ち、「給特法の廃止・抜本的見直し」を求める私たちの思いを叶えるものとはなっていません。決して成立を認めてはならないものです。
「定額働かせ放題」を維持する「改正」案
第1にこの「改正」案は「定額働かせ放題」の給特法の枠組みをそのまま維持するものとなっており、「学校の働き方改革」に逆行するものです。
そもそも現在の「時間外在校等時間」の概念は労働基準法が想定する「時間外労働」ではなく、本質的には「自主的・自発的活動」とみなされるもので、労働基準法36条に定められた労使協定による上限規制(36協定)での長時間労働規制の定めもなく、何よりも「時間外勤務手当」が支給されません。
私立学校や国立学校の付属高校・小中学校の教員に労基法が適用され、時間外勤務手当が支給されている実態をみれば、「教職調整額」の根拠になっている「教員の勤務の特殊性」の主張はもはや破綻しています。すべての公立学校の教員に労働基準法を適用し「時間外勤務手当」を支給すべきです。このことが唯一、最大の解決策です。
改革を削ぐ「教職調整額の段階的引上げ」
第2に「教職調整額の段階的引上げ(現在の4%を2026年1月から5%に引上げ、6年かけて10%にする)を行う」としていますが、このことで教員の処遇が改善されるとする考えは到底理解できるものではありません。
処遇の改善(給与アップ)を行うならば、給与表そのものの改善が必要です。そもそも問題になっているのは長時間労働です。「教職調整額の引上げ」が長時間労働の縮減に繋がる理屈は理解できません。国会議員のように、教員ひとり一人が私設秘書を雇えるぐらいの引上げならともかく「給与がアップしたのだから文句をいわずに働こう」と考えるとでも思っているのでしょうか?このことで「働き方改革」の機運が削がれる要因にもなりかねません。
「時間外労働」の見えない化、ジタハラの進行
第3に、この「改正」案では、都道府県教育委員会や市町村教育委員会に「教員の業務量管理・健康確保等の計画の策定、実施状況の公表を義務づけ」ています。しかし、「給特法」の枠組みが維持されたままでは、むしろ長時間労働の削減には逆効果です。
在校等時間が数値化され公表されるとなれば、既に発生している「とにかく学校から帰れ」という「ジタハラ=時短ハラスメント」が蔓延するのは目に見えています。そして、公にされない「持ち帰り仕事」や「ファミレス残業」が増大するのは明らかです。「時間外勤務の見えない化」がいっそう進行することになります。
管理、分断を持ち込む主務教諭の導入
さらに、第4として、この法案では「組織的な学校運営及び指導の促進」のため、新たな職として「主務教諭」を置くことができるとしています。このことは既にある「主幹教諭」や「指導教諭」とあいまって「教員の管理強化」に繋がるばかりでなく、先行している東京都などの例をみれば、これまでの「教諭」職の給与の引き下げに繋がることが容易に推測できます。
行政職のように、「教諭」→「主務教諭」→「主幹教諭」とならなければ給与があがらない制度になりかねません。「主務教諭」になってようやく現在の「教諭」の給与表と同等というのが先行する自治体の実態です。教員に「管理」と「分断」を持ち込むもので、決して「働き方改革」や「処遇改善」に繋がるものではありません。
今こそ、真の「給特法改正」の実現を
2023年6月、立憲民主党は「給特法廃止・教職員の働き方改革促進法」を衆議院に提出しています。当時は自公与党が多数を占め、野党提出の議員立法は審議に持ち込むのさえ困難な状況でした。与野党逆転に持ち込んだこの状況で、維新も含めた野党に働きかけ、まず、「給特法廃止・教職員の働き方改革促進法」を成立させ、早急に教育公務員に「時間外勤務手当」を支給するための「給特法改正」を実現しなければなりません。
現在の日本の教育の状況は、<教員の長時間労働>が発端となり<志願者減・離職者増>→<教員不足>→<教育の質の低下>につながる危機的状況です。この危機を乗り越えるためには真の「給特法改正」を行わなければなりません。
私たちは政府与党の「改正案」成立に反対し、教員への「時間外勤務手当」の支給を強く求めていきます。