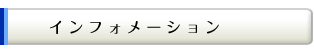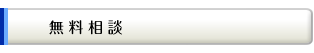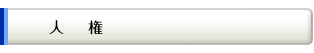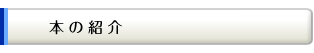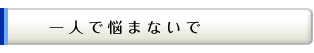日教組人権教育実践交流会

2月22~23日、日教組人権教育実践交流集会が富山市・ホテルグランテラス富山でで開催され、埼玉教組からは椎名書記長と日教組人権教育推進委員でも鳥羽教文部長が参加しました。
初日は丹野日教組中央執行副委員長、熊沢富山県教組執行委員長の主催者挨拶、日教組三大寺中央執行委員の基調報告に続いて、浦秀一尾さん(石川県珠洲市議会議員)「ふたつの災害と人権」をテーマに講演を行いました。
浦さんは石川県教組の組合員として、教員生活を送った後2023年の統一地方選挙で珠洲市議会議員に当選しました。講演では2024年1月1日の能登半島地震と9月の奥能登豪雨の2つの自然災害の被害の当事者であった浦さんがその実態を被災者と支援者双方の視点から語りました。浦さんの精力的な活動に敬意を持つとともに、国の災害対策・対応の不十分さに改めて考えさせられました。
その後、「憲法・子どもの権利条約と人権教育」「部落問題学習のとりくみ」「ジェンダーと人権教育」「インクルーシブ教育」の4つの分科会での実践交流が行われました。
2日目は「イタイイタイ病資料館見学コース」「富山大空襲コース」の2つのコースでフィールドワークを行いました。以下参加者の感想を掲載します。
イタイイタイ病資料館見学コースに参加して
鳥羽大河(児玉・大里支部)
日教組人権教育実践交流会の2日目のフィールドワークは、富山大空襲についてだった。語り部として西田亜希代さん、柴田恵美子さんを迎えた。どちらも富山大空襲を語り継ぐ会のメンバーである。現在太平洋戦争当時のことを語る人が少なくなる中、戦争未経験者が語り部を継いだことは特筆すべきである。特に西田さんは、お父さんが語り部だったという。齢90を超えた今、娘の西田さんが引き継いだという。
1945年8月2日、午前0時36分、アメリカ軍の大型爆撃機B29が富山上空に174機も現れた。中心部には、50万発以上の焼夷弾が投下され、市街地の99.5%を焼き尽くした。被災した人は、およそ11万人、亡くなった人は2700人を超えた。地方都市としては、人口比で最も多くの犠牲者を出した。富山の戦災消失区域図を見ると、市街地から離れた4つの場所に焼失のポイントがある。私も初めて知ったのが、この4つの地点に米軍は、模擬原子爆弾を落とした。7月20日、富山市内3ヶ所、そして26日には、豊田地区に一発の模擬原子爆弾が投下された。広島長崎に落とされた原子爆弾は、このように模擬原子爆弾の練習を経て、投下されていたのだ。
フィールドワークでは、B29からの焼夷弾による熱波から逃れようと人々が集まった神通川の河川敷を訪問した。雪に覆われた河川敷の風景は眩しいばかりだった。空襲当時、この神通川は、人、人、人でごった返したという。熱波から逃れ水を求めてこの川にやってくる。上空から見ると川に逃げる人々はとても目立った。そこを目掛け、B29は焼夷弾を落としていく。神通大橋から下をみると、無数の焼夷弾で、川自体が燃えているようだったという。このような当時の状況を、柴田さんは、熱心に語った。
最後に、富山城址公園内にある「天女の像」を見学した。昭和49年8月1日、戦災復興記念に、富山復興特別事業協議会により建立された。戦後の焼け野原からこの富山市も立ち上がってきた。この町は、被災した多くの人々の苦しみと悲しみの土台の上に今がある。そう考えると感慨深い。ウクライナとロシアの戦争が始まったのは三年前のこと。学校現場でも、戦争について語ることがタブーとなりつつある。戦争は最大の人権侵害である。この言葉を胸に、今回肌で感じた空襲の真実を子どもたちに伝えていきたい。








2-64x64.jpg)