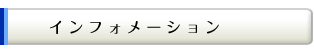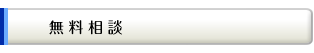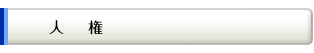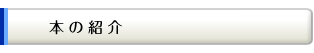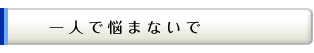「対話」と「探求」の姿勢を続けよう
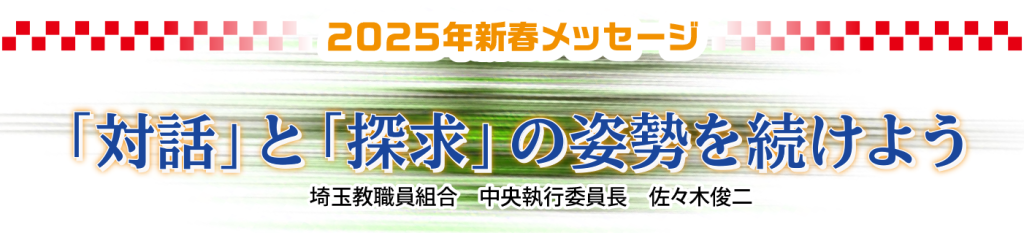

埼玉教職員組合 中央執行委員長 佐々木俊二
新年明けましておめでとうございます。 教育基本法第1条(教育の目的)には「教育は、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値にたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければいけない」と明記されています。
現実の社会状況と見比べながら、どれだけこの目的にそって私たち教員が実践をしているかについて考えていきたいと思います。
まずは最初に平和的な国家及び社会の形成者を育てるために、子どもたちにどんな教育をしているかです。 平和の対義語は一般的には「争い」「戦争」だと思いますが、埼玉大学名誉教授のる暉峻淑子さんは、「戦争・暴力の対義語は平和ではなく『対話』です」と言っています。その言葉を借りるのならば、私たち教職員が日々の活動の中で、どれだけ「対話」を重視しているでしょうか?
目の前の子どもとの対話は当然として、保護者との対話、同僚との対話、管理職との対話がなければ、それは「争い」に転じてしまうといことです。 現実には、多忙化と情報化社会(IT活用)の渦に巻き込まれて、「対話」自体がおろそかになってしまっているのではないでしょうか。
次に「真理と正義を愛する」子どもたちを育てているかどうかについて考えていきたいと思います。 「真理」とは教科書に書いていることだけではありません。既存のメディアが流している情報が真理かどうかもわかりません。新聞やテレビから流れる情報だけでは、「真理」はみえてきません。「正義」という概念もその立場によって大きく違ってきます。私たち大人でさえも、その真理と正義に関しては、よくわからないのが本当ではないかと思います。しかし、それを探求する姿勢ととりくみは、怠ってはいけないのではないでしょうか?。その努力を続けていける2025年でありたいと思っています。